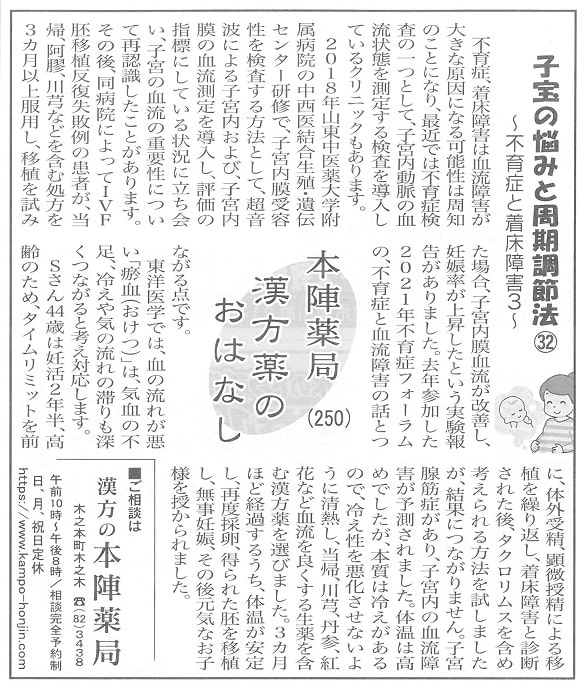滋賀夕刊に掲載中の【漢方薬のおはなし】2022年10月分をご紹介いたします。
バックナンバーはこちら(お悩みの症状に関連する記事を検索していただけます。)
今月は、第250回『子宝の悩みと周期調節法~不育症と着床障害3~』です。
-以下、記事本文-
不育症、着床障害は、血流障害が大きな原因になる可能性は周知のことになり、最近では不育症検査の一つとして、子宮内動脈の血流状態を測定する検査を導入しているクリニックもあります。
2018年山東中医薬大学附属病院の中西医結合生殖・遺伝センター研修で、子宮内膜受容性を検査する方法として、超音波による子宮内および、子宮内膜の血流測定を導入し、評価の指標にしている状況に立ち会い、子宮の血流の重要性について再認識したことがあります。
その後、同病院によってIVF胚移植反復失敗例の患者が、当帰、阿膠、川芎などを含む処方を3カ月以上服用し、移植を試みた場合、子宮内膜血流が改善し、妊娠率が上昇したという実験報告がありました。
去年参加した2021年不育症フォーラムの、不育症と血流障害の話とつながる点です。
東洋医学では、血の流れが悪い「瘀血(おけつ)」は、気血の不足、冷えや気の流れの滞りも深くつながると考え対応します。
Sさん44歳は妊活2年半、高齢のため、タイムリミットを前に、体外受精、顕微授精による移植を繰り返し、着床障害と診断された後、タクロリムスを含め考えられる方法を試しましたが、結果につながりません。
子宮腺筋症があり、子宮内の血流障害が予測されました。
体温は高めでしたが、本質は冷えがあるので、冷え性を悪化させないように清熱し、当帰、川芎、丹参、紅花など血流を良くする生薬を含む漢方薬を選びました。
3カ月ほど経過するうち、体温が安定し、再度採卵、得られた胚を移植し、無事妊娠、その後元気なお子様を授かられました。